産業能率大学総合研究所は15日、「2025年度(第36回)新入社員の会社生活調査」結果を発表した。「年功序列」と「成果主義」のどちらを望むか尋ねたところ、「成果主義」43.6%に対し、「年功序列」は56.3%で「年功序列」を望む回答が「成果主義」を初めて上回った。また、「終身雇用」を望む割合は69.4%、「同じ会社に長く勤めたい」51.8%といずれも増加傾向にあり、“安定志向”の強さがうかがえるとしている。「働く上で最も魅力的と思う環境」については、「仕事はそこそこ大変だが、成長を実感できる」58.8%が「仕事はそこそこ楽で、成長の機会も少しはある」30.6%を約28ポイント上回った。“安定志向”でありつつもほどよいチャレンジを通じ着実に成長できる環境を求めていることがうかがえる結果となった。
https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/research-report/2025/07/15-01.html
ポイント!
「そこそこ」って何?と気になり、データを見てみました。最も魅力的だと思う職場環境を尋ねる質問の項目で、「そこそこ大変」の上に「かなり大変」があり、「そこそこ楽」の下に「かなり楽」がありました。
会社や上司・先輩に求めるものや不安に思っていることなどの割合が高かった項目は、どれもなるほどと感じるものばかりでした。20年以上にわたって回答割合の経年比較されているものがあり、成果主義より年功序列を望む割合が過去一番高かった点について、今後の新人定着のヒントがあるようにも感じました。
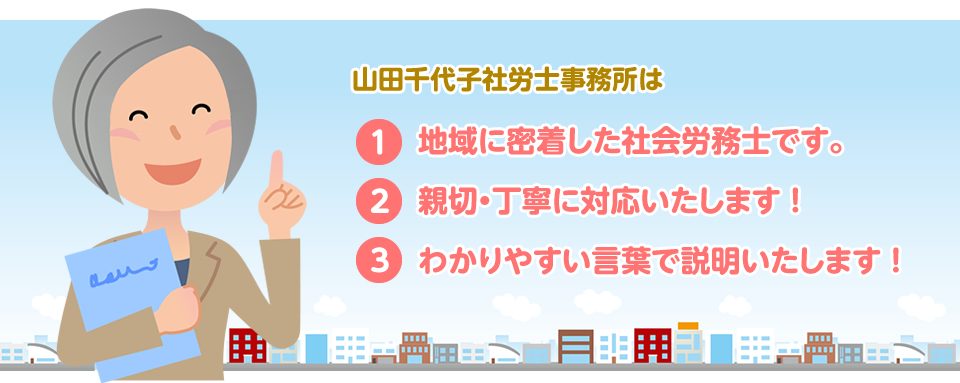
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所