企業で働く意欲のあるシニア社員を積極活用する動きが広がっている。家電量販大手のノジマは80歳が上限だった雇用制限を事実上撤廃。YKKグループも4月に正社員の定年を廃止した。シニア活用を促す制度改正に対応するほか、新型コロナウイルス禍からの経済再開に伴う人手不足を補う。高齢化が一段と進展するなかで、シニア雇用のあり方は企業の競争力にも影響を与えそうだ。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76612390U1A011C2MM8000/
ポイント!
「80歳上限撤廃」は目を引きましたが、上記企業の定年は65歳です。R3年4月1日に施行された70歳までの就業機会確保措置(努力義務)に対しては、年齢での一律雇用維持には限界があるとの意見も見受けられます。
改正法対応を求められている企業としてまず何から実施すべきかは悩ましいところですが、60歳以降の「定年延長」と「再雇用制度」の比較から始められることをお勧めします。
高年齢者雇用安定法改正の概要について詳しいパンフレットが出ていますのでご紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
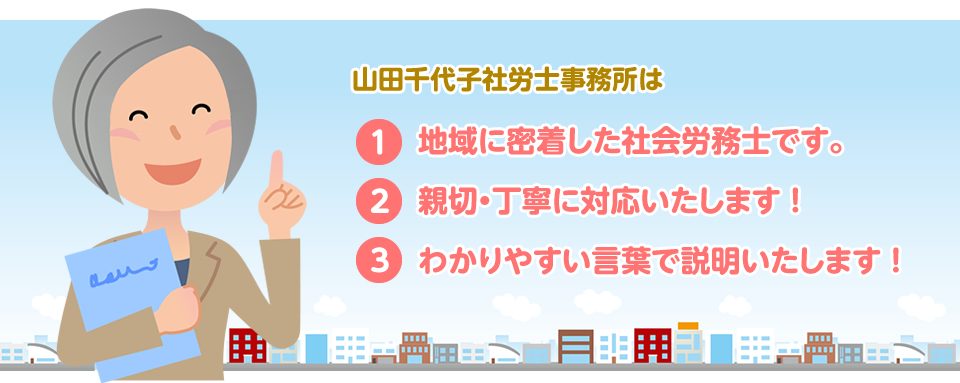
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所