関西経済連合会(松本正義会長)は、企業と労働市場の関係の変化を踏まえた雇用・労働政策に関する意見を取りまとめた。企業が法的リスクを踏まえて新たな人事施策を講じられるよう、公的な労働判例データベースの作成を要望している。データベースは、単に裁判例を収録するだけでなく、過去の結果や変遷を分析・類型化すべきだとした。会員企業からは副業・兼業やジョブ型雇用の広がりにより労働市場とのかかわり方が変わりつつあるなかで、人事判断の予見可能性向上を求める声が多数挙がっていた。
https://www.rodo.co.jp/news/211249/
ポイント!
意見書では、現行の労働基準法制やその他の制度の枠組みが変化する労働環境の実態にそぐわない状況が生じていることを問題のベースとして、働き方と労働移動の二つの観点から望ましい政策の方向性を示すという形で要望項目を何点か示されています。
上記記事はその一部なので、全体を読んでみて意見書への共感というか理解が深まったように感じました。
https://www.kankeiren.or.jp/material/251218ikensho.pdf
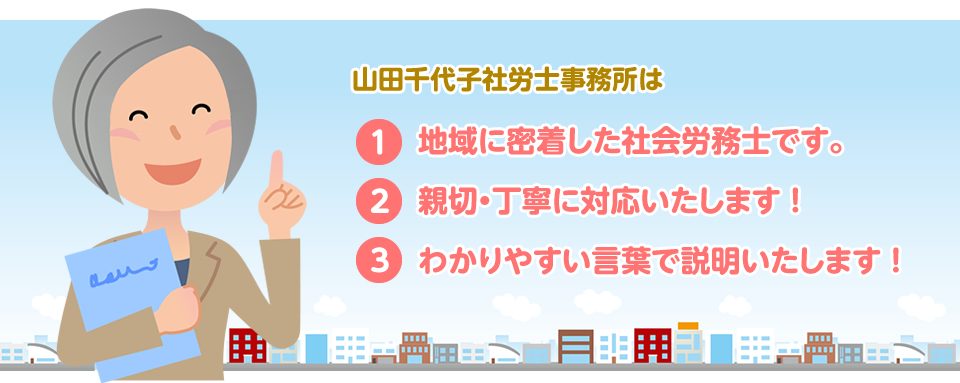
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所