厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備推進のため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」に設定している。労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となった。この制度改正を契機として、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、周知広報に努めていくとしている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html
ポイント!
日経新聞(10/22第5面)の「社長100人アンケート」によると、有給5日間の取得義務化への対応が完了している企業は36.8%で、一方未完了の企業は49.3%(残りは「概ね完了」「あまり対応できていない」)と、人手不足で対応に苦慮されている様子が伺えます。
年次有給休暇の確実な取得については、労働基準法が改正され来年4月1日が施行期日となっています。全企業対象(中小企業の猶予なし)に義務付けられていますのでご注意ください!
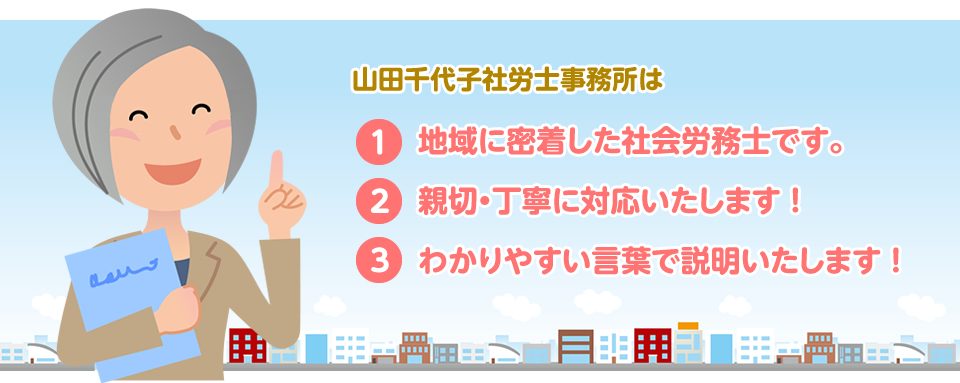
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所