厚生労働省は、2022年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法に対応して、パンフレット「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」を更新した。改正法により、4月からは育児休業を取得しやすい雇用環境整備や妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認が義務化され、10月からは男性の育児休業取得を促進する「出生時育児休業制度」がスタートする。
(改正法概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
ポイント!
令和4年4月1日~施行が迫ってきました。まずは雇用環境整備および個別の周知・意向確認の措置の義務化に加えて有期労働者の育児・介護休業取得要件の緩和となります。何から始めたら良いのか大変分かり難いですが、既存の育児介護休業規程の見直し(確認)から始めてみると案外イメージし易いのではないかと思います。
取っ掛かりとして厚労省の規定例(簡易版)パンフは参考になりそうです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685056.pdf
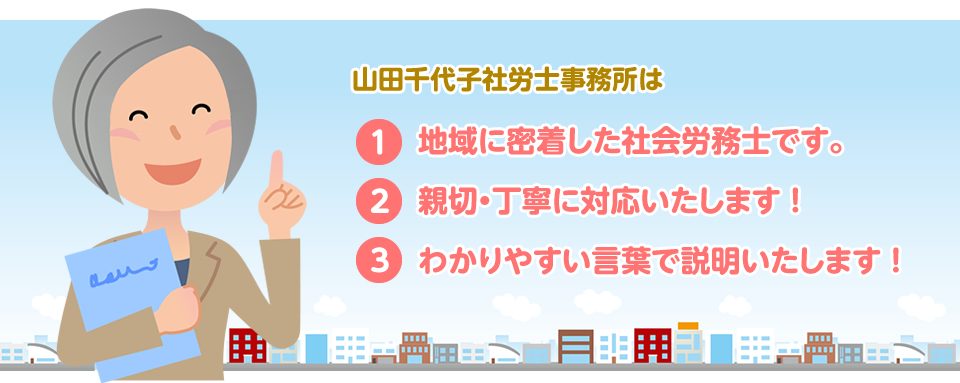
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所