契約更新する期間は「就業規則の範囲内」で「原則5年以内」と契約書に記載して、翌年に雇止めした事案。平成25年にさかのぼって通算5年までとした就業規則の内容は契約更新後に説明された。山口地裁は、以前から生じていた更新の合理的期待が消滅したと解することはできず雇止め無効とした。面接試験に受かれば更新するとしていたが、評価は合理性を欠くとしている。
https://www.rodo.co.jp/precedent/98833/
ポイント!
『5年ルール直前、後絶たぬ雇止め 有期⇒無期雇用 転換めぐり各地で訴訟』11/30朝日新聞でも取り上げられていましたが、最近では雇止め法理が適用される有期契約であると判断された場合は不更新条項の効果も否定される判決が増えてきているとのことです。
長年来て貰っているパートさん、契約社員さんの継続の意向確認は早急に実施する必要ありです。
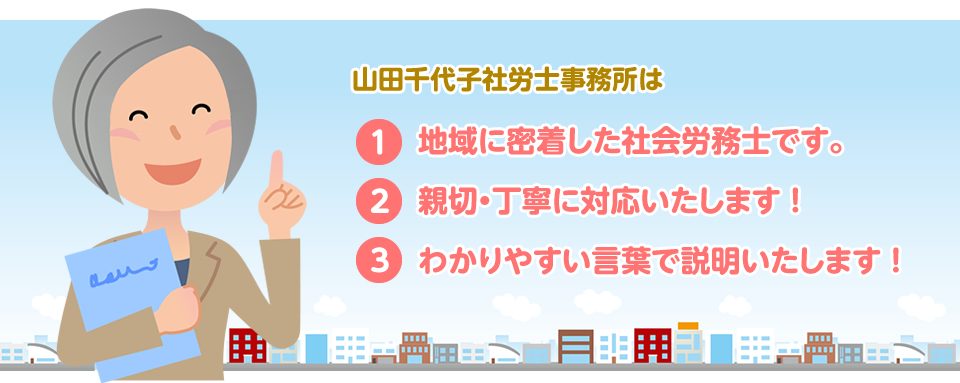
 山田千代子社労士事務所
山田千代子社労士事務所